「また私だけ…」押し付けられる仕事にモヤモヤが募る瞬間
「それ、◯◯さんにお願いしておいたから。」
その一言で、頭の中が真っ白になった。
会議が終わる直前、誰にも相談されていなかった“仕事”が、当然のように自分に割り振られていた──。
別に、頼まれるのが嫌なわけじゃない。
けれど、どうして“あの人”はいつも、自分がやらなくて済むように動けるんだろう?
気づけば私ばかりが、面倒な作業や雑務を引き受けている。
納得いかない。でも言い返せない。
我慢して、ぐっと飲み込んで。
気づいたら、「また私だけ…」とモヤモヤが溜まっていた。
──こんな経験、ありませんか?
職場で“逃げる人”がひとりいるだけで、
空気が変わる。負担が偏る。
そして、その皺寄せはいつも「断れない人」のところにやってくる。
この記事では、そんな 「押し付けて逃げる人」 の実態を深掘りしながら、
なぜ彼らは逃げ続けるのか?
どうすれば自分を守れるのか? を一緒に考えていきます。
あなたがずっと我慢してきたことは、決して小さな問題じゃない。
ここで少し立ち止まって、「それって本当に私が悪いの?」と問いかけるきっかけになれば──。
続きを、ぜひ最後まで読んでみてください。
押し付けて逃げる人の「共通する特徴」
どこの職場にも、一定数いる──
「自分の手は汚さずに済む人」。
その人たちは、見事なまでに責任を回避し、
都合のいいところだけをつまんで仕事をしているように見える。
しかも、要領がいい。
まるで、**「私はその仕事には関係ありません」**というオーラをまとっているように。
たとえば、こんなタイプが思い浮かびませんか?
- 💬 やんわりと頼んできて、断りづらい空気をつくる人
- 👀 常に忙しそうにしていて、話しかけにくい雰囲気を出す人
- 🧾 「◯◯さんがやってくれると思った」と、無責任に他人に振る人
- 😏 成果が出そうな仕事には積極的なのに、面倒事には決して近づかない人
こういう人たちは、**一見すると「うまく立ち回ってるだけ」**に見えるかもしれません。
でも実は、その根底には共通した傾向が見えてくるんです。
✅①“見られていない時”に手を抜くクセがある
誰かが見ている場面ではそれなりに動くのに、
見られていないときにはスッと抜ける。
報告・連絡・相談をせず、フェードアウトする。
この「場面切り替えスイッチ」がうまい人は、
“責任の境界線”を曖昧にして、他人に自然と仕事を押し付ける術を身につけています。
✅②「損得感情」が異様に強い
どんな仕事でも、「自分にとって得か、損か」で判断するクセがあります。
「これはやっても評価されない」→やらない
「これは大変そう」→誰かに振る
それがあからさまでなく、
“うまく自然に”逃げているように見えるのがまた厄介。
✅③責任が曖昧になる“チーム戦”に紛れ込むのが得意
こうしたタイプは、個人プレーではなく、チーム作業の中に紛れることが多いです。
そして、誰がやるのか明確でない仕事に対しては、
「誰かがやるだろう」という態度を取り、
気づいたら“やってくれる人”に押し付ける。
もちろん、本人に悪気はないのかもしれません。
でも、“逃げる”という行動が常態化している人は、
それを「当たり前の処世術」だと信じて疑っていないことも多いんです。
──では、そうした人たちはなぜ逃げる行動を繰り返すのか?
その背景には、意外な“心理の傾向”が隠れているかもしれません。
なぜか“私がやる前提”になっていた、あの日の仕事(体験談)
たとえば、ある日突然「この申請、やっておいて」と渡された書類。
中身を確認すると、自分の部署だけで完結しない内容で、他部署──それも管理職クラスの承認が必要な案件でした。
戸惑って「この件、◯◯部長の了解が必要ですよね?」と聞くと、
返ってきたのは、こんな言葉でした。
「あなた、◯◯部長とよく話してるでしょ?お願いしてきてよ」
……え?
その瞬間、なぜか「自分がやる前提」になっていることに気づき、
モヤモヤがこみ上げてきました。
確かに、たまたま何度かやり取りしたことはある。
でも、それが**“この業務を丸ごと任される理由”になるの?**
なぜその仕事の根本的な段取りや責任の所在まで、自分に押しつけられるのか。
しかも、こうした“上の人の承認を得る系”の仕事ほど、
ちょっとしたミスや表現の行き違いで大きな問題になりかねない。
それなのに──誰もそこに責任を持とうとはしない。
“できそうな人に、なんとなく投げる”
“逃げる人のかわりに、対応できる人がやる”
そんな空気の中で、いつも自分ばかりが最前線に立たされている。
それが、どうしても納得できなかった。
次の章では、その「心の奥」に少し踏み込んでみましょう。
なぜ人は「逃げる」という選択を繰り返すのか?
人が“逃げる”という行動を取るとき、
そこには単なるズルさや怠慢とは別の、深い心理的背景が潜んでいることがあります。
逃げる人の中には、
実は──**「自分に自信がない人」や「傷つきたくない人」**が多いのです。
✅「怒られたくない」「失敗したくない」という恐れ
子どもの頃から、
「失敗=叱られること」
「ミス=評価が下がること」
と刷り込まれてきた人ほど、大人になってもその恐れから抜け出せません。
だからこそ、「やらない」「引き受けない」「関わらない」という
**“防衛的な逃げ”**を無意識に選んでしまうんです。
✅「どうせ私がやっても…」という自己肯定感の低さ
一見、ふてぶてしく見える人でも、
実は心の奥で「自分には無理だ」「失敗するに決まってる」と思っていることがあります。
それを表に出す代わりに、
「自分から距離を置く」「人に振る」という形で回避する。
逃げることで“自分を守っている”んです。
✅「うまくやることが正解」だと信じている
社会に出て、評価や結果ばかりを重視する環境に長くいると、
「頑張るより、うまく立ち回る方が得」という価値観が根づきます。
つまり、“逃げられる状況なら逃げるのが賢い”と本気で思っている人もいる。
そしてそれを**「責任回避」ではなく、「効率的戦略」と信じて疑っていない**ケースもあるのです。
✅でも──逃げること自体は「悪」ではない
ここで大切にしたいのは、
「逃げること=悪」ではないという視点。
私たちだって、限界が来たときは逃げたっていい。
その判断は、自分を守るための選択肢のひとつです。
問題なのは、
**「逃げることが常態化して、他人に負担を押しつけ続けていること」**なんです。
「逃げる人=悪」と一刀両断しても、何も解決しない。
でも、「なぜこの人はこうなるのか?」を知っておけば、
**巻き込まれないための“心のバリア”**を張ることができます。
次のセクションでは、
そんな “逃げる人に押し付けられやすい人”の共通点にフォーカスしていきましょう。
本当に“あなたの性格”のせい?押し付けられやすい人の共通点
逃げる人がいると、
その分、誰かがカバーしなければならなくなる。
そしてその“誰か”は、なぜかいつも、優しくてまじめな人だったりする。
「なんで、私ばっかり…?」
そう感じてしまうあなたは、もしかしたら
**「押し付けられやすい人」**として、無意識に“選ばれて”しまっているのかもしれません。
✅① 「頼まれると断れない」優しさと責任感
まわりの人が困っていると、放っておけない。
言われたことはきっちりこなすし、自分の役割に誇りを持っている。
だからこそ、「お願いがあるんだけど…」と言われると、
つい「いいですよ」と答えてしまう。
本来、それは素晴らしい長所。
でも職場によっては、**「断らない人」=「押しつけ先」**と見なされてしまうんです。
✅② 「嫌われたくない」という思いが先に立つ
断ったら冷たく思われるかもしれない。
角が立つのは嫌だし、人間関係を壊したくない。
そう思うがゆえに、
“引き受けることで関係を守ろう”としてしまう。
でもその結果、
「◯◯さんに頼めばやってくれるよ」という認識が広まり、
どんどん自分だけが負担を抱える構造になっていきます。
✅③ 「自分ならできる」という思い込み
まわりが気づいていない中でも、
「あ、これやらないとまずいな」と察して行動できる。
そういう“空気の読める人”ほど、
何も言われなくても手を出してしまうんです。
でも──
やれるからやる、は美徳じゃない。
やってしまったことで、
「やるのが当たり前の人」になってしまうのは、悲しいことです。
✅④ 「自己犠牲こそ正しい」という価値観
「周りの人が楽になるなら、私が大変でもいい」
「自分が我慢すればうまく回るなら、その方がいい」
そう信じてきた人は、
気づかないうちに“自分の時間と心”を削り続けています。
でも、それが限界を超えた時──誰も守ってはくれません。
だからこそ、“やさしさの矢印”を一度、自分に向けてあげてほしいんです。
あなたが押し付けられてきたのは、
あなたの「人としての魅力」が原因でもある。
だからこそ、ここで一度立ち止まって、
**「どうやって自分を守るか」**を考えてみることが、とても大事なんです。
次の章では、そんな“優しさゆえに損をしてしまう人”が、
現実的にできる【対処法】について、一緒に考えていきましょう。
どう対処する?「仕事を押し付けられた時」の実践的な工夫
「逃げる人は仕方ない。私は私を守らないと。」
そう頭ではわかっていても、
実際の現場で“うまく断る”のは難しいものです。
相手との関係を気まずくしたくないし、何より、
“冷たい人”と思われるのが怖い。
だからこそ、
相手にダメージを与えず、自分を守る方法を身につけておくことが大切です。
✅① 「言い換え」で断るスキルを身につけよう
いきなり「無理です!」と強く言う必要はありません。
少し言い方を工夫するだけで、断りながらも角が立たなくなります。
たとえば──
- 「確認が必要なので、今すぐは判断できません」
- 「その件は、私の手がいっぱいで対応が難しいかもしれません」
- 「◯◯さんの方がその分野に詳しいと思いますよ」
直接的に否定せずに、“やんわりスルー”する言い回しを
いくつか持っておくと、とっさの場面でも冷静に対処できます。
✅② 曖昧な仕事には“言語化”と“記録”で境界線を引く
「◯◯さんがやると思ってました」
「え? それって私の仕事じゃないんですか?」
──こうしたトラブルが起こるのは、
“誰が何をやるか”が曖昧な状態のまま進んでしまうからです。
だからこそ、以下のような工夫が効果的です👇
- チャットやメールで「今の業務分担の確認です」と一言添えて送る
- 打ち合わせのメモを共有して、“決定事項”を明文化する
- 「念のため確認ですが〜」と前置きしながら、線引きの意識を持つ
これだけで、“押し付けられる構造”がグッと減ります。
✅③ 上司に相談する時は「感情」ではなく「事実」を伝える
もし押し付けがあまりにも続くようなら、
我慢し続けるのではなく、適切なタイミングで上司に相談することも大切です。
その際に注意すべきは、“怒り”や“被害者意識”ではなく、
「業務の不均衡による支障」という切り口で話すこと。
たとえば──
- 「今のタスクが重なっていて、対応に限界が来ています」
- 「このままだと納期や品質に影響が出そうなので、分担を再確認したいです」
こうした“事実ベース”の言い方なら、感情論にならず、
冷静な職場改善の相談として受け取ってもらいやすくなります。
✅④ 普段から「線引きできる空気」をつくっておく
いざという時に断れない人ほど、
普段から「なんでも引き受ける人」という印象が強くなりがち。
だからこそ、日常的に少しずつ、
- 「今、手一杯なんですよね〜」
- 「この件終わったら次いきますね」
などの**“自己主張のサイン”**を、
軽いトーンで発信しておくことが大切です。
そうすることで、
“断ることがある人”というポジションを少しずつ築けます。
✅⑤ それでも無理な時は──「逃げてもいい」
ここまでいろんな工夫を挙げてきたけれど、
それでもどうにもならない時は──「離れる」という選択肢も大事です。
責任感の強い人ほど、
「ここで踏ん張らないと…」と自分を追い込んでしまいがちだけど、
理不尽な職場にすべてを捧げる必要はありません。
あなたが心と体を壊す前に、
“立ち去る自由”があることも、忘れないでください。
ここで紹介した対処法の中から、
あなたが「これならできそう」と思えるものを、
ひとつでも実行できれば、それは確実に**“守る力”の一歩**になります。
次のセクションでは、
逃げる人たちが最終的にどうなっていくのか──
**“逃げ癖の末路”**について見ていきましょう。
✅⑥【例文つき】“突然の雑務”を押し付けられたときの返し方(実例集)
押し付けの中でも特に多いのが、
**「今ちょっとこれ、やっておいてくれる?」**と突然振られる雑務系のタスク。
いきなり対応を求められると、戸惑いながらも「断る理由が見つからずに受けてしまう」──
そんな経験、ありませんか?
ここでは、そんな場面で使える**“やんわり断る”フレーズ例**をいくつか紹介します👇
✅ケース1:自分の手がふさがっている場合
「今ちょっと、これお願いできるかな?」
🗣**「申し訳ないですが、今◯◯の作業が立て込んでまして…、
今手を離してしまうと納期がずれ込むかもしれません」**
🗣**「確認したいのですが、この作業、私の方で対応する優先度になっているでしょうか?」**
👉 ポイント:“今すぐ対応できない”状況を説明+責任の所在をあいまいにしない
✅ケース2:ちょっとのつもりで繰り返し押し付けられるとき
「あ、これだけ。すぐ終わるからお願いね〜」
🗣**「なるほど、すぐ終わりそうですね。ただ、今手元に処理中の案件があるので、
その後に回してもいいですか?」**
🗣**「内容を確認してからお返事したいので、資料だけ先に送ってもらえますか?」**
👉 ポイント:“即時対応”をかわす+判断を引き延ばす柔らかテク
急に振られた雑務ほど、
「これくらいなら…」と引き受けてしまいがち。
でも、そうした“積み重ね”が、
「あの人は何でもやってくれる」認識を強めてしまうのです。
だからこそ、一言断る勇気を持つことが、
“押し付けループ”を断ち切る第一歩になります。
“逃げる人”は最終的にどうなるのか──逃げ癖が招く未来
今はうまく立ち回っているように見える“逃げる人”。
でも──
本当に、ずっと逃げ切れるのでしょうか?
周囲の人たちは、気づいています。
「いつも責任から逃げる人だ」
「この人に任せると、自分が大変になる」
そんなふうに、“静かに信頼を手放されていく”のです。
✅① 任されなくなる
逃げる人が最初に直面するのは、
「仕事が回ってこなくなる」という現象です。
最初は「ラクできる」と思うかもしれません。
でも実際は、「あの人には期待できない」と判断され、
重要な仕事から外されていくのです。
それは同時に、
評価のチャンスも、成長の機会も、失うということ。
✅② キャリアが“薄っぺらく”なっていく
責任ある仕事に手を出さず、
成果に直結する仕事も避け、
「関わっていない」ことを武器にして過ごしてきた人のキャリアは──
振り返ったとき、中身のない履歴だけが残ります。
社内でポジションを失うだけでなく、
次の転職でも「何ができるのか」が証明できない。
逃げて得た時間の代わりに、信用もスキルも失っている。
それに気づくのは、たいてい手遅れになったあとです。
✅③ 人間関係の“本音の部分”で孤立する
表面上はうまくやっていても、
同僚や部下、時には上司からも、
“あの人は信用できない”という目で見られるようになります。
口に出しては言わないけれど、
大事な仕事の場では呼ばれなくなる。
相談されなくなる。頼られなくなる。
そして徐々に──
**「いてもいなくても変わらない存在」**になっていくのです。
✅④ 自分の「逃げグセ」に気づけないまま年を重ねる
一番厄介なのは、
こうした“逃げ癖”が染みついている本人が、
その危うさに気づけないこと。
自分を正当化し続け、
「うまく立ち回ってる」と思っていても、
実際は“ただ責任から逃げていただけ”だった。
そして気づいた頃には、
誰からも期待されず、信頼されず、
「逃げることで得たもの」よりも、「失ったもの」の方がはるかに大きかった──
そんな未来が待っているのです。
逃げることは、一時的には“楽”かもしれません。
でも、逃げることに慣れてしまうと、人は成長のチャンスを失う。
読者であるあなたは、そうはならない。
ちゃんと向き合って、考え、踏みとどまる力がある。
だからこそ、
**“逃げ癖を持つ人と距離を取ること”**は、自分を守る上でも、賢明な選択なのです。
逃げ癖の“結末”を見たことがある──ある同僚の話(体験談)
実際、以前の職場にいたAさんがまさにそうでした。
「穏やかで人当たりもいい人」だったのですが、
新しい仕事が回ってくると、いつも
「あ、それ僕より〇〇さんの方が得意だと思いますよ」と
うまくすり抜けてしまうタイプで、責任のある業務は自然と遠ざかっていきました。
ある日、先輩がこぼしていたのを覚えています。
「Aさん、感じはいいんだけどね…なんか、“いつも他人事”っていうか。任せづらいんだよな」
本人はというと、特に自分の立ち位置に疑問を持っていない様子で、
「今の仕事、ラクでいいですよ。定時で帰れるし」なんて笑って話していました。
でも数年経ったころ、役割はほとんど誰でもできる雑務ばかりになり、
昇格の対象にも挙がらず、最終的にはひっそりと退職していきました。
その後も何社か職場を変えていたようですが、
「あの人、何ができる人なのか、よくわからなかったね」
と話していた同僚の言葉が、ずっと耳に残っています。
信頼を失うのに、大きなミスは必要ないのかもしれません。
「逃げ続ける」ことで、気づかぬうちに自分の土台が削られていく。
そんな現実を、私はAさんの姿から学びました。
逃げそうになったけど、踏みとどまった人の話(体験談)
もうひとつ、印象的なエピソードがあります。
私の知人Bさんは、かつて大きなプロジェクトの責任者を任された際、思うように進まない状況に直面し、「辞めたい…」と何度も口にしていました。
「もう逃げちゃおうかな」
「別に私じゃなくてもいいし…」
そんな言葉をぽつりとこぼす彼女を、私は何度も見てきました。
けれど、Bさんはある日、ふとこんなことを言ったんです。
「この苦しさから逃げたら、たぶん、また次も同じことを繰り返す気がする。だから今回は残ってみる」
そして彼女は、自分なりに小さな改善から手をつけていきました。
資料の見せ方を変え、メンバーとの会話の頻度を増やし、できることを一つずつ丁寧に。
半年後、プロジェクトはなんとか成功にこぎつけ、Bさんの表情は以前よりずっと自信に満ちていました。
「あのとき逃げなかったことで、今は少しだけ誇れる自分になれた気がする」
そんな彼女の言葉に、私は深く心を動かされました。
逃げたくなる瞬間は、誰にでも訪れます。
けれど、「もう一歩だけ頑張ってみよう」と踏みとどまった経験は、その人に確かな足跡を刻んでくれるのかもしれません。
それはきっと、後になって初めて気づく“成長の証”なのだと思います。
次は、「そもそも、なんでこういう構造が生まれてしまうのか?」──
“職場環境の問題”という視点から、少し深掘りしてみましょう。
問題の本質は“人”ではなく“職場環境”にあるのかもしれない
ここまで読んできて、
「なんでこんな人がのさばるんだろう?」
「私ばっかり損してるじゃないか」
──そう感じた人もいるかもしれません。
でも、実はこの“押し付けと逃げ”の構造、
その人自身の問題だけでなく、「環境そのもの」が育ててしまっているケースもあるのです。
✅① 評価制度が曖昧な職場では、逃げ得がまかり通る
誰がどんな働き方をしていても、
上司が細かく見ていない。
評価の基準も曖昧で、「やったもん負け」になってしまう。
こうした環境では、
真面目な人ほど消耗し、ズルい人ほど得をする構造ができあがります。
逃げる人がのさばるのではなく、
**「逃げても問題にならない職場風土」**が放置されているのです。
✅② 上司が“放任主義”or“気づいていない”問題
チームマネジメントがうまくいっていない職場では、
人の負担や不満が可視化されず、
「押し付ける人 vs 押し付けられる人」の構造が放置されます。
特に、上司が「自分の目の届く範囲しか見ていない」タイプだと、
見えないところで責任逃れや不公平な負担が横行しやすくなります。
悪いのは、逃げている人だけじゃない。
“見ようとしない管理者”もまた、逃げの片棒を担いでいるのです。
✅③ 「いい人が損をする」文化は、組織を腐らせる
「誰もやらないから私がやる」
「文句を言っても仕方ないから我慢する」
そんな“自己犠牲”が回り回って正当化されると、
次第にそれが「当たり前」になっていきます。
誰かが理不尽を訴えても、
「前からそういう職場だから」
「仕方ないよね」
──で、終わってしまう。
まじめな人が潰れて、ズルい人が生き残る職場。
それが健全な職場なわけがありません。
✅④ 本当に変えるべきは、“働く環境そのもの”かもしれない
もし、何をどう対処しても押し付けが止まらない。
逃げる人が何人もいて、誰も何も言わない。
上司に言っても響かない。
──そんな職場に身を置いているとしたら、
もはやそれは、**個人の工夫や努力だけではどうにもならない“組織の病”**です。
あなたが消耗しながら、その場に踏みとどまる理由はあるでしょうか?
本当に守るべきものは、仕事ではなく「自分自身」なのではないでしょうか。
このセクションは「逃げる人」ではなく、
“逃げやすい空気”を作ってしまっている背景構造に目を向ける時間でした。
そして次は、この記事の最後。
すべてを読んでくれたあなたに、言葉を贈るまとめのパートです。
最後に──“自分の責任”にしないという強さを、あなたへ
あなたがこれまで抱えてきた悔しさや、
理不尽さや、どうにもできなかったあの場面たち。
それらはすべて、**「自分が弱いから」「断れないから」**なんて理由で
片付けられるようなものじゃありません。
あなたが感じてきた“やるせなさ”は、
本物です。
そしてそれは、**あなたが“ちゃんと向き合ってきた証拠”**でもあるのです。
「また押し付けられた」
「自分だけ損してる気がする」
「誰も気づいてくれない」
──そんなふうに思ってしまった自分を、どうか責めないでください。
責任を負うべきは、
逃げ続けている人や、問題を見ようとしない職場環境の方です。
あなたが悪いんじゃない。
むしろ、あなたはずっと“正しくあろう”としてきた人です。
でも今、この記事を読み終えたあなたは、
もう一歩、先に進むことができます。
無理に変わらなくていい。
だけど、“守る意識”は、今日から少しずつ持ってみてください。
- 「できない」と言っていい
- 「やりたくない」と思っていい
- 「私ばかり」と感じたら、立ち止まっていい
その強さは、きっとあなた自身の未来を守ってくれるから。
そして、どうか忘れないでください。
この世の中には、
“ちゃんと見てくれている人”も、きっといます。
あなたの頑張りを、
あなたのまじめさを、
あなたの優しさを。
逃げずに向き合ってきたあなたが、
“本当に安心して働ける場所”に出会えることを、
心から願っています。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
あなたの心が、少しでも軽くなっていますように。

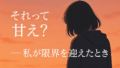

コメント